ホーム > 業務紹介 > 【コラム】教えて、「東北育種場」のお仕事 > 海を越えてやってきた侵略者との120年の戦いⅡ
更新日:2023年12月22日
ここから本文です。
海を越えてやってきた侵略者との120年の戦いⅡ
前回、“海を越えてやってきた侵略者との120年の戦い【プロローグ】”では、マツ枯れについての基本的なこと、そして、マツノザイセンチュウを継代しながら研究室で飼っていることをレポートしました。今回はマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発の本丸、接種検定(の準備まで)についてです。
まず、接種検定の対象となる候補木、マツノザイセンチュウに抵抗性があると思われるマツを見つけます。マツ枯れの激甚被害地で生き残ったマツであれば、もしかすると抵抗性があるのでは?と考え、この木を候補木とします。候補木から種子を取ってきて苗木を育てます。(この辺のことは、次回触れたいと思います。)
これにマツノザイセンチュウを接種して、枯れない個体を探すのです。
この接種検定を行うための準備、まずはマツノザイセンチュウの大増殖です。
接種するためには大量のマツノザイセンチュウが必要。大増殖のために行うことは基本的に【プロローグ】の回で説明した継代の時と同じですが、培地をジャガイモ寒天から麦に変えます。麦培地にすると増殖する数が格段に増えるのです。
まず、培地の準備。シャーレに麦とお砂糖(砂糖水)を少々、これをオートクレーブという圧力鍋のお化けのような機器で滅菌、柔らかく調理【写真-1】。
これにボトリチス菌をのっけて、まずは餌を増やそう【写真-2】。
そして、ボトリチス菌で真っ白となったシャーレにマツノザイセンチュウをのっけて大増殖【写真-3】。餌、食べ放題ですね。
この麦培地での増殖を繰り返して、線虫の数を増やします(この作業も、雑菌が増えないよう慎重に・・・)。これらの工程を【図】に示しましたが、これで分かるとおり、作業を始めてから大量増殖が終わるまでに、一ヶ月ぐらいかかります。接種は7月に行うので、逆算して作業日程を決め計画的な実施が重要。この作業が上手くいかないと、この年の接種検定ができなくなり検定が1年遅れてしまうのです。
 |
 |
 |
|
【写真-1】麦培地の準備 |
【写真-2】餌の準備 |
【写真-3】マツノザイセンチュウ大増殖① |

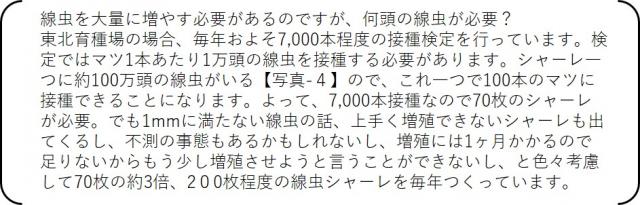
さて、増殖が終わった麦培地の中にいる線虫をどうやって取り出すかというと・・・
水の中で
さらに、これをメスシリンダーで正確な水の量に調整して、ピペットで1mL抽出【写真-9】。この時、線虫はすぐに沈んでしまうので、ビーカーの中の水を混ぜて線虫が均等に漂うようにして素早く抽出。そして顕微鏡を覗きながら数えていきます【写真-10】【写真-11】。結果、これで1mL中にいる線虫の数が分かるので、あとは【写真ー9】で調整した水の量を掛け算すれば、線虫の総数が分かる!!!
この抽出&勘定作業、グズグズしていると水の中に大量の線虫がいることから窒息死してしまいます、一連の作業はテキパキと!作業が終われば速やかに冷蔵庫に移して、線虫の活動を弱め、接種に備えましょう。
準備は整いました。いよいよ実際に接種していきましょう。次回です。
 |
 |
 |
|
【写真-4】マツノザイセンチュウ大増殖② |
【写真-5】マツノザイセンチュウ抽出装置 |
【写真-6】線虫抽出中 |
 |
 |
 |
|
【写真-7】線虫沈殿中 |
【写真-8】線虫回収中 |
【写真-9】線虫抽出中 |
 |
 |
 |
|
【写真-10】線虫勘定中 |
【写真-11】数取機(カウンター)でカシャカシャ |
【写真-12】線虫一杯 |
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.
