ここから本文です。
平成24年度トピックス
平成24年度林木育種推進東北地区技術部会を開催
- 12月13日と14日の両日、東北育種場において「平成24年度林木育種推進東北地区技術部会」が開催されました。
会議初日は、関係各県におけるマルチキャビティコンテナによる育苗に関する取り組み状況の紹介があったほか、第二世代精英樹の今後の配布計画や今年度のマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発状況等について情報交換や議論がなされました。 2日目は関係各県と東北育種場各課の個別打合せが行われました。
 |
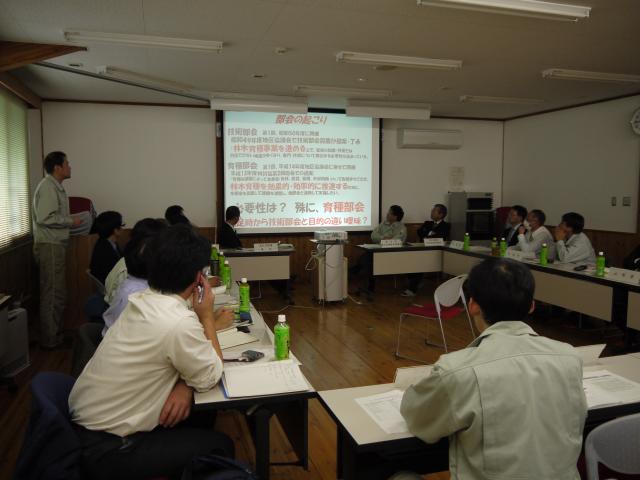 |
 |
秋田県の林業団体「創森会」が来場
- 11月1日、秋田県の林業団体関係者14名が林木育種事業に関する研修のため東北育種場に来場しました。
研修は林業経営技術の向上に必要な知識を習得することを目的に行われ、育種場職員から次世代精英樹選抜事業やマツノザイセンチュウ抵抗性育種事業等の概要説明があった他、ミニチュア採種園も見学しました。
参加者の皆さんからは、マツノザイセンチュウ抵抗性品種の早期流通や、次世代精英樹に対して大いに期待している等、意見や励ましの言葉をいただき有意義な研修となりました。
 |
 |
 |
滝沢村立滝沢第二小学校に対する出前授業と見学
- 10月5日、滝沢村立滝沢第二小学校からの依頼を受け、復興教育の一環として林木遺伝子銀行110番による奇跡の一本松増殖に関する授業を行いました。
授業では、増殖に至った経緯や作業当時の職員の考えや心構えについて、当時を振り返りながら説明しました。生徒たちからは、「無事に里帰りしてほしいので頑張って育ててください」、「とても大切な仕事なのでこれからも頑張ってください」等といった激励の言葉をもらいました。また、同日の午後にはつぎ木4兄弟の見学にも訪れました。
 |
 |
 |
スギの球果を採取
- 4月に行ったスギ次世代精英樹候補木同士の人工交配により結実したスギの球果を採取しました。今後、球果を乾燥させ採取した種子を来年の4月に苗畑に播種します。この苗木は、スギ次世代精英樹開発のための試験地に植栽される計画です。
 |
 |
 |
|
3月に袋がけをしたスギの枝 |
袋を外して球果を採取します |
乾燥させ種子を精選します |
次世代精英樹候補木の選抜作業
- 9月に入り、スギ次世代精英樹の候補木選抜作業が本格的に始まりました。今回は山形県内の検定林3箇所から約20本を選抜し、個体ごとに樹高や胸高直径、ヤング率や通直性の調査を行いました。今年度は、雪が降り出す前の11月上旬頃までに、残り5箇所で選抜作業を行う計画です。
|
|
 |
滝沢村立一本木小学校の生徒が来場
- 9月6日、滝沢村立一本木小学校の生徒がつぎ木4兄弟見学のため来場しました。
この見学は、今月4日に育種場職員が同小学校に出向いて行った奇跡の一本松の後継樹育成の取り組み紹介と一連の行事で、つぎ木4兄弟を見学して震災復興の取り組みを学ぶとともに、震災を風化させないことを目的に行われました。
生徒たちからは、どのようにつぎ木4兄弟を育ててきたのかなどの素朴な質問があり、丁寧に説明することで理解を深めている様子でした。
 |
 |
 |
滝沢村立一本木小学校で出前授業を実施
- 9月4日、滝沢村村立一本木小学校で奇跡の一本松に関する出前授業を行いました。
この授業は、同校が行っている震災復興教育の一環として奇跡の一本松の震災直後から現在に至るまでの様子やつぎ木4兄弟の育成状況を知ることで、震災を風化させないことを目的に行われています。
当日は5年生と6年生を対象に後継樹育成に関する取り組みについて説明を行いました。生徒達は熱心に耳を傾け、「歴史に残る松になってほしい」など自分たちの気持ちを発表していました。
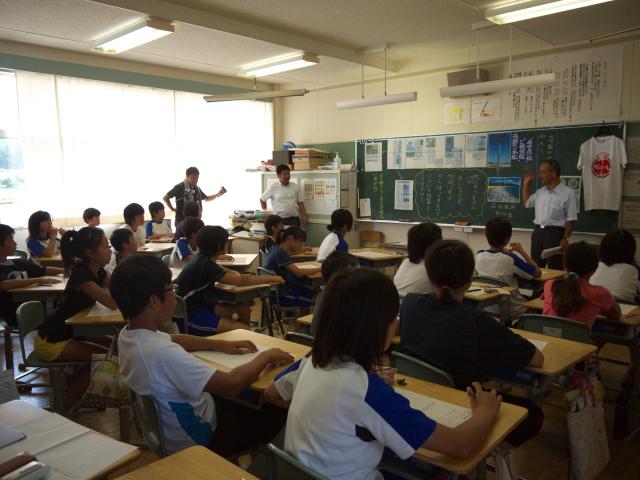 |
 |
第2回東北地区高速育種運営会議・平成24年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議育種分科会を開催
- 7月23日~24日にかけて、第2回東北地区高速育種運営会議および平成24年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議育種分科会が山形県山形市・東根市で開催されました。
初日の高速育種運営会議では、関東育種基本区で行われた次世代精英樹の原種配布の事例や東北育種基本区での今後の配布スケジュール等について説明がありました。
林業研究・技術開発推進東北ブロック会議育種分科会では、新たな東北育種基本区の林木育種事業推進計画の提案があった他、関係機関からの要望事項で震災の津波で大きな被害を受けた海岸松林の再生に向けた、基本区内における今後の抵抗性マツの供給体制の方策やスケジュール等について情報提供がありました。
2日目は奥羽増殖保存園で現地検討会を行い、スギエリートツリーの開発やマルチキャビティコンテナを用いた育苗に関する取り組みの紹介・説明があり活発な意見交換が行われました。
 |
 |
 |
盛岡市立下橋中学校の生徒が職場体験のため来場
- 7月10日、盛岡市立下橋中学校の生徒6名が職場体験のため来場しました。
樹高や胸高直径の調査、測桿鎌での採穂、ツツジのさし木増殖など、普段の授業では体験できない作業ばかりだったせいか試行錯誤しながらも、元気いっぱいに積極的に取り組んでおりました。
東北育種場では、小・中・高校・大学からの実習や見学を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
 |
 |
 |
平成24年度東北林試協林木育種専門部会を開催
- 6月26~27日、東北育種場において平成24年度東北林業研究機関連絡協議会林木育種専門部会が開催されました。
会議では、各県での重要な研究課題について議論が交わされたほか、抵抗性マツを核とする松くい虫や塩害に強い海岸林の再生に向けた各県での取り組みや、次世代精英樹の開発に向けた取り組み、各県で取り組んでいる研究内容等について紹介・議論が行われました。
 |
 |
 |
マツノザイセンチュウの接種検定を実施
- 6月22日、マツノザイセンチュウの接種検定を行いました。
接種検定は、苗木の当年に成長した部分をペンチで潰して溶液と混ぜた体長1mm程度のセンチュウ約1万頭をスポイトで注入します。この検定でセンチュウに対する抵抗性を調査し、抵抗性品種を開発することが目的です。
今回は、約3,000本の苗木に接種を行いました。この中から枯れずに生き残ったマツは、センチュウに対する抵抗性を持つ品種として東北育種基本区内で普及されることとなります。
良い結果が出ることが期待されます。
 |
 |
 |
中村久須志神社の杉が里帰り
- 6月6日、青森県鰺ヶ沢町の「中村久須志神社の杉」が里帰りを果たしました。
中村久須志神社の杉は、町の天然記念物に指定されている推定樹齢600年の古木で、平成19年に採穂・増殖してもので、当日は、神社の宮司の他4名の氏子の方々立ち会いのもと、境内内に2本が植栽されました。
 |
 |
|
宮城県で剪定講習を実施
- 5月28日、宮城県林業技術総合センターにおいて採種穂園の剪定に関する技術指導を行いました。
東北育種場から2名の職員が派遣され、スギの採穂木やヒノキの採種木の剪定技術について実技を交えながら指導しました。宮城県からは10名の職員が出席し、剪定技術を習得するため熱心に作業に取り組んでいました。
 |
 |
スギ次世代精英樹候補木からの採穂
- 成長等の面において、より優れた性能を示すスギ次世代精英樹を開発するため、東北育種場では今年度も次世代精英樹候補木からの採穂に取り組んでいます。
採穂した穂木は、さし木やつぎ木で増殖され発根性・初期成長量等を調査し、次世代精英樹や初期成長の優良な品種の開発に用いられます。
 |
|
|
採穂した穂木 |
岩手大学農学部生が増殖実習のため来場
- 5月24日、森林造成学実習の一環として岩手大学農学部の3年生26名が来場し、増殖実習を行いました。
当日は、さき木用としてツツジ・ムラサキシキブ・ニシキギを、つぎ木用としてスギをそれぞれ採穂しました。刃物を使った作業ということもあり、学生の皆さんも最初は緊張した面持ちでしたが、職員の指導の下、無事作業を終えることが出来ました。
 |
 |
 |
 |
|
学生の皆さんが行ったツツジ等のさし木とスギのつぎ木苗 |
|
高校生がつぎ木4兄弟取材のため来場
- 5月21日、岩手県立盛岡第三高校放送部の生徒4名が、奇跡の一本松の後継樹育成について放送コンクールでの発表題材とするため取材に訪れました。
生徒の皆さんからは、増殖に至った経緯や取り組むうえで注意した点等について質問していました。
 |
 |
種子播き付け作業
- 4月25日、スギ・アカマツ・クロマツ・ブナの種子の播き付け作業を行いました。播いた種子に薄く土を被せその上からわらで覆い、風に飛ばされたり鳥の食害から防ぐためワラや寒冷紗をかけます。
スギとクロマツはつぎ木用台木として、アカマツはマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発に必要な苗木として育苗します。
 |
 |
 |
|
作業説明の様子 |
参加者による植え付け |
植え付け後の風景 |
スギ次世代精英樹開発のための人工交配
- 4月13日、スギの次世代精英樹開発のため人工交配を実施しました。この準備作業として、3月9日に次世代精英樹候補木の雌花に交配袋を被せています。今回は、花粉銃を用いて交配袋に花粉を注入しました。種子は今年の10月頃に採取され、来年の春、畑に播かれます。その後、2~3年の育苗期間を経て育てられた苗木は、次世代精英樹開発のための試験地に植栽される予定です。
 |
 |
 |
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.



