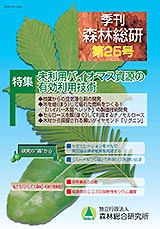2018年2月28日発行 |
季刊 森林総研 No.40
特集:無花粉スギの研究最前線
- これまでに見つかった色々な無花粉スギ
- 遺伝マーカーで無花粉スギを判別する
- 不定胚に由来する無花粉スギ苗の大量増殖
- 少花粉スギ品種と無花粉スギ品種の開発に取り組む
- ゲノム編集で無花粉スギを作る
|

2017年11月30日発行 |
季刊 森林総研 No.39
特集:木を使って守る生物多様性
- 歴史資料から知る過去の林野利用
- 林業が生物多様性の保全に果たす現代的な役割ー若い植栽地の価値ー
- 生物多様性の鍵となる渓畔林の役割とその管理
- 木材を使うことと、生物多様性を守ることの両立をめざす森林管理
- 伐採地でふえる花粉媒介昆虫たち
- 南の島の希少なキツツキ ノグチゲラの住宅事情と人の暮らしの関わり
- 小面積皆伐で人工林の樹木の多様性を保全する
- トドマツ人工林における保残伐施業の実証実験
- 森林計画制度における生物多様性ー市町村の取り組みー
- 木材貿易が生物多様性に及ぼす影響
|

2017年8月31日発行 |
季刊 森林総研 No.38
特集:出口に近づくバイオマスマテリアル利用
- 日本の森から採れる工業材料「改質リグニン」
- 地域材を原料にしたセルロースナノファイバーの一貫製造と利用
- 衝撃に強い木材・プラスチック複合材ープラスチックに代わる新素材ー
- 竹の効果的な利用をめざして
|

2017年6月30日発行 |
季刊 森林総研 No.37
特集:減災研究の最前線
- 雪崩の進行を妨げた森林
- 海岸林が津波を弱める効果は林の構成によってどう変わるのか?
- ベトナムの地すべり災害を防止する研究開発
- 防災のための詳細な地形データの活用
|

2017年2月28日発行 |
季刊 森林総研 No.36
特集:森の文化力 ―「地域」の「ひと」と「くらし」を支える森林―
- 山菜をめぐる地域文化
- 地域の歴史と文化を刻むやんばるの森
- 森林・林業と文化的景観
- 地域の文化を守るヨーロッパの自然公園
- 地域の森林と学校
- 森林体験と教育
|

2016年11月30日発行 |
季刊 森林総研 No.35
特集:空から森を観る
- リモートセンシングによる森林観測
- 機動性を活かしたドローンの森林・林業現場への活用
- 森林での災害把握に役立つ空中写真と人工衛星画像の利用
- 航空機LiDARによる森林の三次元計測
- 地球観測衛星の画像を利用した森林資源の広域評価
- 南米アンデスにおける森林のモニタリング
|

2016年8月31日発行 |
季刊 森林総研 No.34
特集:出土木材と仏像に使われる木材
- 遺跡出土木材から知る日本人と樹木とのつながり
- 古代一木彫像の用材樹種の識別
- 近赤外線で壊さずに木彫像の材料を明らかにする
- 木の香りで木彫像の樹種を識別
- 樹木の年輪が持つ情報とその利用
- 年輪の酸素同位体比で木材の産地を判別する
|

2016年5月31日発行 |
季刊 森林総研 No.33
特集:面白い微生物ワールド
- 本当は偉い! 生きた木を腐らせるきのこ「生立木腐朽菌」
- コモン菌根ネットワーク 木の根は菌でつながっている
- 樹木病原菌の光と影
- 空気を養分に変える ―窒素固定細菌の働き―
- 地球は線虫に包まれている
- 世界のいろいろな松茸
|

2016年2月29日発行 |
季刊 森林総研 No.32
特集:サクラの科学最前線
- サクラを創ってきた歴史を紐解く
- サクラ栽培品種の系譜をたどる
- DNAから見たサクラの栽培品種
- ‘はるか’を増やす
- サクラと病気
- サクラは温暖化で早く咲くのか?
|

2015年11月30日発行 |
季刊 森林総研 No.31
特集:期待される木質バイオマスエネルギー
- 木質バイオマスのエネルギー利用を取り巻く状況
- 木質バイオマスエネルギーで地方創生
- 木材から都市ガスを作り出す
- 破砕による木質バイオマスのエネルギー資源化
- 木質バイオマス発電の採算性を評価する
- エネルギー作物としてのヤナギの可能性
|

2015年9月11日発行 |
季刊 森林総研 No.30
特集:森林と水循環
- 間伐すると森林からの水流出量が増える
- 森林に積もる雪と溶ける雪を探る
- 気候変動と森林流域の水流出
- 沖縄本島北部のリュウキュウマツ人工林における水循環
- 熱帯モンスーン地域の水循環に乾燥常緑林の高木が果たす大きな役割
- 水源林造成事業による森林の水源涵養機能発揮
|

2015年5月29日発行 |
季刊 森林総研 No.29
特集:今後の再造林の推進に向けた低コスト化研究
- 低コストな再造林の作業システムをつくる
- コンテナ苗の活用とこれからの課題
- 低密度植栽と大苗植栽
- 低コスト化のための下刈り回数の省略
- 低コスト林業に役立つ「エリートツリー」の普及は特定母樹で
|

2015年3月3日発行 |
季刊 森林総研 No.28
特集:地球温暖化研究の今
- 地球温暖化研究の今
- 将来予測からみたわが国の森林分野の緩和策
- 温暖化への自然林の適応策
- 気候変動に適応した強靱な森林をめざして
- 森林と大気の間で吸収・放出されるCO2を直接測る
- 観測ネットワークによる東アジアの森林炭素量を把握する取り組み
- 森林分野の緩和策と適応策のベストミックスを探る
|

2014年12月8日発行 |
季刊 森林総研 No.27
特集:CLT開発の現状 地方創生の切り札「シーエルティー」
- CLTとは
- 欧州におけるCLTの現状
- 日本におけるCLTの現状
- 国産材CLT開発に向けた森林総研の取り組み
- CLTの今後
|

2014年9月24日発行 |
季刊 森林総研 No.26
特集:世界自然遺産 小笠原諸島は今
- いのち繋がる島々の大きな変化
- グリーンアノールの脅威
- 絶滅の淵からの脱出
- 変えてはいけない自然/変えるべき自然
|
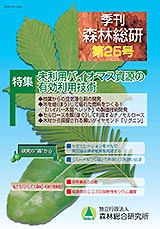
2014年6月16日発行 |
季刊 森林総研 No.25
特集:未利用バイオマス資源の有効利用技術
- 枝葉からの空気浄化剤の開発
- 木を焙(ほう)じて優れた燃料をつくる!「ハイパー木質ペレット」の製造技術開発
- セルロースを解(ほぐ)して利用するナノセルロース
- 木材から採掘される黒いダイヤモンド「リグニン」
|

2014年2月28日発行 |
季刊 森林総研 No.24
特集:安全かつ省力的な新しい生物害防除技術
- 菌類を利用したスギ花粉飛散防止技術の実用化に向けて
- カツラマルカイガラムシの被害拡大を食い止める技術
- 菌床シイタケ栽培の害虫対策 ―ナガマドキノコバエの侵入防止は時刻に気をつけて―
- ヒノキ根株腐朽病に対応するには
- おとり木トラップ法によるナラ枯れ対策
|

2013年11月30日発行 |
季刊 森林総研 No.23
特集:きのこ研究最前線
- マツタケとその仲間の類縁関係
- 広葉樹をマツタケの宿主にすることに成功
- 魅力ある乾シイタケの作出
- プルシアンブルーを用いた栽培きのこの放射性セシウム低減技術
|

2013年8月31日発行 |
季刊 森林総研 No.22
特集:森ではたらく林業機械 ―安全で効率的な木材生産を可能にする―
- 自走式搬器の自動化
- 自動追従走行型車両の開発
- 自動植付機の開発
- バイオマス対応林業機械の開発
- 林業機械と運転者を効果的に保護するには
|

2013年5月31日発行 |
季刊 森林総研 No.21
特集:熱帯林と地球環境を守る仕組み
- REDDプラスとは
- 森林の炭素蓄積量を推定する
―地上調査からのアプローチ―
―空からの森林モニタリング―
―地上調査を補う新しい技術―
- 熱帯林減少の要因と対策
- REDDプラス技術解説書
クックブックの刊行
- REDDプラスの実現のために
|