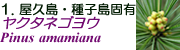種の特徴

クロビイタヤは、5つに切れ込んだ葉が美しい落葉高木である。宮部金吾が北海道の日高地方を調査した時に発見したので、彼が初代園長を勤めた北大植物園のシンボルマークにもなっている。
クロビイタヤは日本固有種で、北海道南部(十勝・日高・胆振・石狩・渡島支庁)および東北北部(青森・秋田・岩手県)と中部山岳(福島・群馬・長野県)とに隔離分布している。2003年に渡島支庁の七飯町でも自生個体が見つかったので、北海道南部から東北北部までは連続的に分布していると言えるだろう。
本種の染色体数は、多くのカエデ属の種と同じく2n = 26で、二倍体である。性表現は、雄性両全性同株(同じ株に雄花と両性花がつく)とされている。しかし、北海道千歳市での観察によると、機能的には雌の両性花と雄花があり、個体レベルでは両性株(73%)・雌株(7%)・雄株(20%)に分けられた。木のサイズが小さいと雄株が多い傾向があった。さらに、両性株は雌雄異熟性を示した。他家受粉とくらべて自家受粉では結実率が半減し、部分的な自家不和合性があった。花にはさまざまな昆虫が訪れ、ケバエ科(Bibionidae; Diptera)のハエが花粉媒介に貢献していた。果実は、翼がほぼ水平に開き、密な毛がある。受粉失敗や近親交配によって、果実の中に種子がない「しいな」を作ることがある。種苗育成のためには、種子が充実した果実を選んで確保する必要がある。
果実に毛がない個体は、シバタカエデ(var. shibatae (Nakai) Hara)として区別され、 中部山岳(福島・群馬・長野県)にのみ自生し、長野県の菅平高原ではクロビイタヤと混生している。シバタカエデも同様に、絶滅危惧IB類に指定されている。
東北地方を境として北日本と中部山岳とにクロビイタヤの分布が隔離されているのはなぜか、また、中部山岳にだけ自生するシバタカエデはどのように由来したのかは、まだわかっていない。このような北日本と中部山岳との隔離分布は高山植物などで知られており、次のような歴史が推測されている。第四紀更新世に氷河期と間氷期が繰り返され、植物は適した気候帯を追って移動していた。氷河期に日本列島を南下した植物は間氷期に北上したが、中部山岳にその一部の集団が取り残されることもあっただろう。そのような隔離集団は間氷期に遺伝的に分化し、その次の氷河期に北に逃れた集団が東北地方まで再び南下した。このようにして、遺伝的に分化した集団が北日本と中部山岳とに分かれて分布するようになったと考えられている。おそらく、中部山岳のクロビイタヤは氷河期に南下して取り残された集団であり、北日本の集団とは遺伝的に分化しているかもしれない。また、シバタカエデは、さらに古い氷河期に中部山岳に定着し分化した種かもしれない。両者が混生していても遺伝的に混じり合っていないとしたら、何らかの生殖隔離の機構が両者の間にあるだろう。

クロビイタヤの葉と翼果.
衰退要因

クロビイタヤの好む生育地は、河川に沿った湿った土地である。特に、河川の周りの自然堤防などに多く見られることから、河川撹乱にともなって更新していると思われる。母樹の周りには稚樹がよく見られ、林冠ギャップができて明るくなると、成長して林冠に達すると考えられる。
豊かな河辺林が残されている地域ではクロビイタヤは多く見られるが、人為的な土地利用を受けている地域では、生育地が断片化している。北海道千歳市では、千歳川やその支流に沿って河畔林や防風林が残され、市街地やその郊外でクロビイタヤを見ることができる。しかし,その生育地は住宅地や農地によって分断され、クロビイタヤの集団は断片化している。それらの断片化した分集団でも母樹は結実し、その周囲の樹冠の下には稚樹が見られる。よって、断片化によってすぐに次世代の更新が絶たれるわけではない。
しかし,種子生産や交配様式は断片化の影響を受けていた。農地や住宅地によって断片化した集団を調べたところ、個体数の少ない集団の果実ほど種子充実率が低いことがわかった。100個体以上の成木がある防風林では種子充実率が24%だったのに対し、周辺500 m以内に他個体がいない孤立木では1%に満たなかった。一方、農地によって分断された集団の間では、個体数の少ない集団でも遺伝子流動は保たれていた(図)。しかし、市街地にある集団では、送粉昆虫が少なかったり、それらの移動が妨げられるために、遺伝子流動が減少した。このように、断片化した集団では、個体数が種子生産量に、周辺環境が遺伝的流動に影響しているようだ。

図.クロビイタヤが分布する千歳市の景観(左上)、成木の分布位置(左下)、断片林ごとの種子充実率(右上)および種子血縁度(高い値ほど近縁で遺伝子流動が少ない)(右下). 暖色は値が高く、寒色は値が低い.
保全のための課題と対策

クロビイタヤは、低標高の河川沿いに生育し、葉や果実の形に特徴があるため、その生育を確認しやすい。開発によって失われる可能性のある生育地を発見し、見守っていくことが重要である。
具体的な保全策は次のとおりである。
①生育地の確認と維持
林縁などの明るい場所には稚樹が定着している場合が多いので、それらを育成することによって生育地を維持していくことができるだろう。
②周辺環境を含めた保全
断片化した生育地では、媒介昆虫の移動を助ける周辺環境の存在が重要である。このため、農地などの周辺環境も含めた保全が求められる。
③移植用種苗の採集方法と由来への留意
母樹から種子を採集して育成する場合、孤立木や断片化した生育地では、ほとんどの果実が「しいな」であるおそれがある。個体数の多い大きな生育地の種子を用いることが望ましい。
ただし、北日本と中部山岳とに隔離分布するクロビイタヤは、地域によって遺伝的に分化していると考えられる。そのため、地域を越える種苗の移動は避け、地元の種苗を用いるべきである。