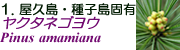種の特徴

ケショウヤナギは、急峻な山岳から平らな扇状地に流れ出る河川の礫質の河畔に生育し、樹高30 mに達する高木である。幼木の枝や幹がしばしば白粉で覆われ、小枝は繊細で紅色を帯びて美しいことから「化粧柳」と名付けられた。本種は、ヤナギ属(Salix)とオオバヤナギ属(Toisusu)とは異なるケショウヤナギ属(Chosenia)に分類されていたが、系統解析によってこれらはひとつの系統群にまとまることがわかったため、今はヤナギ属に分類されている。ケショウヤナギはオオバヤナギとの間で雑種をつくり、これはカミコウチヤナギと呼ばれ、長野県の上高地周辺でまれに見られる。
ケショウヤナギは、萌芽などによる栄養繁殖をほとんどせず、実生によって更新している。雌雄異株で4月下旬から5月上旬に開花する。花粉は風媒である。綿毛の付いた種子は6月下旬頃おもに風によって散布される。種子は、水分条件がよければ一日で発芽し、種子の寿命は3週間以内とされている。実生が定着する立地環境は、おもに礫によって構成され、水分条件が厳しい、光条件が非常によい砂礫堆に限られている。このためケショウヤナギは、河川の撹乱によって生じた砂礫堆に、優占度の高い一斉林を形成する。このような一斉林は、洪水の撹乱を受けてしばしば破壊されるが、撹乱を免れた林分は、他のヤナギ科やカバノキ科の樹種が優占する林分と融合し、先駆樹種の若齢林となる。
北海道の歴舟川では、約14年で開花結実が始まり、撹乱によって平均寿命は約37年に限られている。河川の流路が大きく変わり若齢林が撹乱を受けなくなると、ケショウヤナギは成熟して最大約100年と言われる寿命を迎え、ハルニレやヤチダモ、ウラジロモミといった遷移後期種の群落へと移行する。
このような生活史と個体群動態の特徴は、分布の隔離性や希少性に大きな影響を与える。本種は、バイカル湖の東部から東シベリアと極東にかけて広く分布し、世界的に見れば広域に分布する普通種である。島嶼部では、サハリンと北海道、本州に分布し、千島列島や他の島では記録されていない。日本では、北海道と長野県に隔離分布し、本種が記録された2次メッシュ(標準地域メッシュシステム)は北海道で59メッシュ、長野県で6メッシュである。それぞれの地域でも分布は隔離性を示している。北海道では、分布の中心である十勝地方から大雪山系によって隔てられた紋別市と、日高山脈によって隔てられた浦河市に分布する。長野県でも、梓川の上高地と松本盆地との間でダム群によっておもな生育地が隔てられている。

写真.長野県のケショウヤナギ集団(上高地)
衰退要因

ケショウヤナギのような寒冷気候を好む樹種は、最終氷期(最寒冷期の約2万年前)以降の気候温暖化で分布が北方に縮小してきたと考えられる。したがって、将来の地球温暖化によって、さらに分布域が縮小し、隔離集団が絶滅するかもしれない。
また、本種のような河畔性の樹種は、護岸工事などによる流路の固定化や、ダムの流量調節による氾濫の減少のために、実生が定着できる立地が失われるおそれがある。このような河川の人為的改変の影響を、北海道における59メッシュの成木個体数レベルと25メッシュの過去50年間の減少率レベルから推測した。減少率レベルは、絶滅が1メッシュ、1/100-1/10が1メッシュ、1/2-1が23メッシュで、成木個体数レベルを考慮すると50年後と100年後における絶滅確率はともに0%であった。2000年刊行の環境庁(当時)レッドデータブックでは、長野県の6メッシュと北海道の2メッシュの情報にもとづいて絶滅確率を推定したために、100年後に10%以上の推定値を得て、E基準で絶滅危惧II類に指定した。しかし北海道の集団にとって、このランクは過大評価とされ、2007年公表の環境省レッドリストにはケショウヤナギは記載されなくなった。しかし、長野県の集団は絶滅が危惧される状況にあることに変わりない。
長野県の松本盆地では、外来種のニセアカシアが河畔で繁茂することによりケショウヤナギの生育を阻害している。氾濫原の植生遷移によってケショウヤナギ林は衰退してしまうが、ニセアカシアは定着する立地環境が広く成長が旺盛なためその遷移過程を加速している。そのため、ケショウヤナギ林が存続できる期間や面積が縮小しているようである。
保全のための課題と対策

ケショウヤナギのように、河川撹乱によって生じる生育地に更新し、成木の寿命が限られている樹種では、やがて枯れてしまう特定の樹木を保護するよりも、世代交代が可能な河川の生態系を維持することが重要である。河川管理には、防災や取水、漁業などさまざまな目的があるので、社会的な合意のもとに、行政による保全対策を検討することが必要である。有効な対策は立地環境によって変わるので一般化はできないが、具体的には次のような保全策が求められる。
①河川管理における更新サイトの確保
種子生産や散布の能力の高さや、礫質の氾濫原に限定された実生定着などの特性を活かす更新サイトを確保する。
②隔離分布集団間の移植の禁止
隔離分布する種の場合、たがいに離れたそれぞれの集団を独立に保全する必要がある。なぜなら、各集団は地理的に隔離しているため、遺伝的に分化している可能性があるからである。ケショウヤナギの種子の散布距離は30 kmに達することを示唆する事例があり、花粉や種子が風に乗って河川の間を移動できると思われる。しかし、葉緑体と核の遺伝子を用いて遺伝的分化を調べたところ、長野県と紋別市の集団は十勝地方の集団と核の遺伝子において大きく分化していることがわかった。また、核の遺伝子の変異(多様性)は、長野県と紋別市、特に松本盆地で、大きく低下していることもわかった。一方、葉緑体の遺伝子は北海道と長野県と同じタイプであった。これらのことから、隔離集団は異なる系統に属するとは言えないが、隔離後に互いに異なる遺伝的組成に分化したと言える。隔離集団の遺伝的多様性が低下しているが、近親交配の増加や適応遺伝子の喪失によって生存や繁殖が脅かされない限り、隔離集団の歴史的由来を継承するためにも安易な移植は避けるべきであろう。

写真. 長野県のケショウヤナギの生育地(安曇野)