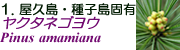種の特徴

アポイカンバは、北海道様似町のアポイ岳のみに分布する固有種である。本種は四倍体で、成熟しても樹高1mほどの低木にしかならない矮性のカバノキである。矮性カバノキはヒメカンバ類と呼ばれ、おもに北極周辺のツンドラ地帯に生育している。氷河期には、日本列島にもヒメカンバ類が広く分布していたと考えられている。日本に生き残っているヒメカンバ類には、アポイカンバの他にヤチカンバがある。
アポイカンバは、ダケカンバとヤチカンバとの雑種に起源することが、核DNAの塩基配列を用いて明らかになった。ダケカンバとヤチカンバとの交雑は、最終氷期が終わった約1万年前から約8千年前までの気候温暖化によって、ヤチカンバの生育地にダケカンバが分布を拡大して生じたと考えられる。雑種に起源する種では、親種に由来する遺伝子を組み合わせることによって、親種にない形質が進化することがある。アポイカンバは、湿地性のヤチカンバと高山性のダケカンバに由来する遺伝子の組み合わせによって、アポイ岳の特殊な環境に適応した独立種に分化したのかもしれない。
日高山脈の南端に位置するアポイ岳は、超塩基性のカンラン岩を母岩とするため、ヒダカソウに代表される特殊な高山植生が成立している。また、沖合を流れる寒流から夏季に濃霧が発生し、日射量の減少と気温の低下によって生育する植物種が限られている。アポイ岳山頂から西に延びる稜線「馬の背」と南の尾根にある「幌満お花畑」の岩隙・岩砕・未風化土壌にアポイカンバが生育している。特に、馬の背の中央部に多い。それらの高山植生の面積は、1988年の空中写真から判読すると4.3 haで、アポイカンバの生育個体数は2,350、結実個体数は430と推定された。
一方、ダケカンバは、山頂部と谷筋に沿って生育し、アポイカンバと混生している所もある。ダケカンバの花粉をアポイカンバに交配すると、同種他家受粉より種子の充実率と発芽率が低く、両種の間に交配後生殖隔離が存在する。しかし、発芽可能な種子ができるので、この生殖隔離は完全ではない。アポイ岳で両種は5月中旬から下旬に開花する。アポイカンバの開花はダケカンバより早く始まり、両種の開花期は重なる。また、個体内では雄花序が雌花序より早く咲く。よって、アポイカンバの雌花序は、ダケカンバの雄花序と開花期が重複しやすく、ダケカンバからアポイカンバへの種間受粉が生じていると考えられる。


写真. アポイカンバの雄花(左)、雌花(右)
衰退要因

アポイ岳の高山植生は、植生遷移によって衰退しつつある。1954年から1999年にわたる観察によると、ハイマツ群落やキタゴヨウ・ミヤコザサ林、ダケカンバ林が拡大し、高山植生の面積が減ってきた。遷移後植生は多様で、未熟土壌へのホシガラスによる種子散布からハイマツが定着・成長する系列、ノガリヤス・チャボヤマハギ・エゾススキによる土壌形成からミヤコザサ・キタゴヨウ林への系列、裸地化した崩壊地でのダケカンバ林への系列が認められている。また、1970年以降、ハイマツとキタゴヨウの個体数の増加が顕著になり、ハイマツの年枝成長量も増えている。さらに、近年のエゾシカの増加により、高山植物の食害も観察されている。
ヒダカソウやエゾキスミレ、ヒダカイワザクラなど、山野草家に人気のある高山植物は、盗掘によって1970年以降減少してきた。1997年には幌満お花畑のヒダカソウが計画的盗掘を受け、開花個体数が大幅に減少した。その後は、盗掘防止のための監視によって大規模な盗掘は減ってきている。
アポイカンバは、アポイ岳の他の高山植物種と比べると、盗掘や踏みつけ、植生遷移の影響はほとんどなく、個体数は全体として安定している。ただし、幌満お花畑では個体数が少なく、ハイマツからの被圧によって枯死する個体もある。生育地中心部の馬の背登山道沿いの撹乱された場所には再生個体がわずかに見られるが、生育地周辺部では実生更新はほとんどないと思われる。
アポイカンバの種子生産は受粉量によって制限されている。なぜなら、人為的に十分な花粉量を与えた他家受粉よりも自然受粉の方が種子充実率が低く、母樹のまわりの60 m以内の同種個体数が増えると自然受粉の種子充実率が高くなったからである。新規加入がほとんどない現状では、種子の量と質が低下しても、アポイカンバの短期的な個体数変動にはそれほど影響がないだろう。しかし、将来、自然撹乱や再生事業によって更新場所が生じる時には自然受粉による種子の量と質の低下が問題となる。ただし、アポイカンバの受粉技術は確立しているので人為交配による種子の確保は可能である。
保全のための課題と対策

アポイカンバは、アポイ岳の高山植生を特徴づける構成要素であり、高山植物群落の全体を対象として保全を進めていく必要がある。近年、衰退しているアポイ岳の高山植生を保全するための具体的な対策は次のとおりである。
①高山植生の盗掘防止
盗掘防止の取組みは、地元NPOによって1998年より進められている。2006年には、北海道希少野生動植物保護条例に基づき、ヒダカソウ生育地の保護を目的として、登山道外部への立ち入りが制限され、幌満登山口から幌満お花畑の間の登山道が閉鎖されている。
②高山植生の衰退防止
高山植生の衰退を止めるには、ハイマツの伐採や侵入する草本の除去などによって遷移の進行を抑制する必要がある。そのような積極的な植生管理には異論もあり、現行の法制度では実施が難しい。これらの問題に取り組むため、アポイ岳再生委員会が2008年に発足し、特別天然記念物に指定された1952年当時の高山植生の再生と復元を目指している。そして、高山植物再生実験地を設け、防鹿柵設置・裸地化・播種による高山植生の再生を試みている。
③ジオパーク指定による環境教育の推進
2008年には、ユネスコが支援するジオパークにアポイ岳が認定された。ジオパークとは、科学的に貴重で美しい景観の地形や地質を保全し、教育・研究・地域振興に活用する国際的な活動である。これによって、アポイ岳で環境教育などの活動が活発になるだろう。


写真. アポイ岳の生育地(左)とアポイカンバ(右)
(永光輝義/森林遺伝研究領域)