�ڎ�

| ���͂��߂� | |
|
������ۑS�̂��߂� | |
|
�P�D����̌���Ɛ�łւ̈��z�� |
|
| �����킲�Ƃ̌���ƕۑS�� | |
�͂��߂�

���A�E�n���T�~�b�g�ō̑����ꂽ�������l���ۑS���Ɋ�Â��āA���{���{��2007�N�Ɂu��O���������l�����Ɛ헪�v�����肵�A�������l���̕ۑS�Ǝ����\�ȗ��p��ڎw���Ă��܂��B���̂Ȃ��ŁA�n��ɂ�����l�Ǝ��R�̊W���č\�z���邽�߁A���A���̐����ł����ԂÂ���ւ̎��g�݂��f�����Ă��܂��B
�L���Ȏ��R���ւ���{�ɂ����Ă��A���݁A�ۊǑ��A���̂S��ɂP�킪��Ŋ뜜��Ƃ���A�������l���̊�@�͌����Ė����ł͂���܂���B����ꂽ�n��ɕ��z��������ۑS���邱�Ƃ́A�������l����ۑS�����ŏd�v�ȈӋ`�������܂��B
�X�ё����������ł́A�X�͊����琶���c��A���݂ɂ��̎p���Ƃǂ߂Ă���k���n�̊���𒆐S�ɁA���L�̐X�ѐ��Ԍn���\�����A�������l���ۑS�̂��߂ɓ��ɏd�v�ƍl�����邳�܂��܂Ȋ���̕ۑS�����Ɏ��g��ł��܂����B�����̐��ʂ����ƂɁA��ʓǎ҂ɂ��킩��₷���L�q��S�����āA��Ȋ���ۑS�̊Ǘ��}�j���A���Ƃ��Ă��̍��q���쐬���܂����B�����Ɏ��^����Ă��Ȃ�����̕ۑS����l�����ł��Q�l�ɂ��Ă��������A�n��ɂ��������̕ۑS�Ǘ��Ɋ��p���Ă���������K���ł��B
����ۑS�̂��߂�

�P�D����̌���Ɛ�łւ̈��z��
����́A����ꂽ�n�����L�̐�����ɋǒn�I�ɕ��z���Ă�����̂������B�ߋ��̋C��ϓ��ɂ���ĕ��z�悪�k����������̑����́A���̕S�N���x�̊Ԃ��}���ɐ��ނ��Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�X�͊��ɓ��{�ɍL�����z���A��ꖜ�N�O����n�܂����C�g���ɂ���Ėk���ɕ��z�悪�k�������k���n�⑶��𒆐S�ɁA�X�ё����ł͂��܂��܂Ȋ���̕ۑS������i�߂Ă����B���̌��ʁA����̑����͒����I�ɂ͎��R�J�ڂ̉e�����Ă�����̂́A�������̐���n�Ǝ�����̎������X�V����T�C�g�̌�����A�X�V�s�ǂ��s�ǂ������炷�l�דI�v���ɂ���Đ��ނ��Ă��邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�B���̌�����܂Ƃ߂�ƁA��łɌ��������z�̒��ɂ������̎p�������Ă���i���}�j�B

�}�D����̐�łւ̈��z��
���Ȃ킿�A�X�є��̂�A�сA�͐�⎼�n�ł̓y�n�J���Ȃǂɂ���Đ���n�̌����╪�f�����N����A�����̐�����������i�@�j�B���ɁA�e�ƂȂ錻���̐�����������ƁA�������������Ď�q���Y���ቺ���A�ߐe��z�ɂ���Đ�����ɐB�̔\�͂��Ⴂ�q�������܂�A�X�V�s�ǂ������N�������i�A�j�B�܂��A������t���̒蒅�ɓ��L�̐�������K�v�ȏꍇ�́A�X�ъǗ������Ȃǂɂ���čX�V�T�C�g���������A������̐��̌������i�ށi�B�j�B����ɁA������̐N���ɂ�鐊�ނ�a���b�Q�ɂ���Q�������A����s�ǂ������炷�i�C�j�B���̂悤�ɂ��āA��łɌ��������z���n�܂�̂ł���B
�{���q�łƂ肠��������ɂ��āA��Ȑ��ޗv�����T�ς���ƁA���̂悤�ɓ����Â��邱�Ƃ��ł���i���ʓ��̐����́A�Y���������̔ԍ��j�B
�@�����̐��̌����F�S�Ă̊���B
�A��`�q�𗬂̐����E�ߌ��㐨�ɂ��X�V�s���F�ɂ߂ċǒn�I�ɌŗL�ɕ��z�������i�� 1, 2, 3, 6, 13�j�A���n������i�� 9, 10, 11�j�B
�B�X�V�T�C�g�̌����ɂ�鎟����̐��̌����F�J���}�c�A�тɂ��������������������R�ѐj�t���i�� 3�j�A�͐�̔×�����J�n�E���n���X�V�T�C�g�Ƃ������i�� 4, 5, 9, 10, 11, 12�j�B
�C ����s���F�l�דI�ړ����n����ю��ӊ��ւ̋�����̐N�����N�����Ă������i�� 4, 7, 8, 10, 11�j�B�a���b�Q�ɂ���Q���Ă������i�}�c�ސ����a�i�� 1�j�A�V�J�H�Q�i��3�j�A���M�H�Q�i�� 8�j�Ȃǁj
�Q�D����ۑS��
���̂悤�ȏɂ������������I�ɕۑS���邽�߂ɂ́A�P�ɐ���n��ی삷�邾���ł͏\���łȂ��ꍇ�������B���ꂼ��̒n��W�c�ɂ����鐊�ޗv���𖾂炩�ɂ��A��łɌ��������z�̗����f����K�v������B����܂ł̌�������A�K�v�Ƃ����ۑS�������ƁA����7���ڂ������邱�Ƃ��ł���B
(1) ����n��̌Q�̃��j�^�����O
�����F�����A���̌���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ́A���ʓI�ȕۑS������߂邽�߂ɂ܂��K�v�Ȃ��Ƃł���B
���ɁA�͐�̔×����⎼�n���ɐ��炷�����i�� 4, 5, 12�j�ł́A�y�n�J����͐���C���傫�Ȑ��ޗv���ƂȂ邽�߁A�l�דI�����ɂ��r���̊Ď������߂���ꍇ�������B�܂��A�ɂ߂ċǏ��I�ɕ��z�������i�� 2, 3, 7�j�ł́A���R�̐A���J�ځE���R���ނ��̂��̂̔c�����K�v�Ƃ����P�[�X���ڗ��B
����̔������̂���r�I�V�������r�\���i�M�i�� 5�j�́A��1�����ȃ��b�h���X�g�i����12�N�j�ł́A�u��Ŋ뜜IB�ށv�Ƃ���Ă����B�������A���̌㐸�͓I�ɒ������s��ꂽ���ʁA����ɐV���ȕ��z�n����������A�����̐�������錻���{�����m�F���ꂽ���߁A��2�����b�h���X�g�i����19�N�j�ł́u��Ŋ뜜II�ށv�ƃ����N�͉��������B�V���ȕ��z�n�̔����́A����n�̂���n��ɂ����ă��r�\���i�M�ւ̗�����i�߁A�n��ɂ�����ۑS�ւ̓����������炷�Ƃ����g�y���ʂ������炵���B
����A���ȃ��b�h���X�g�ɂ́u���s���v�Ƃ���������f�ڂ���Ă���B���̒��ɂ́A����A����n�ł̌����炩�ɂ���邱�ƂŁA��Ŋ뜜�̃��x�����オ��\���̂�����������ƍl������B�Ⴆ�A�k�C���ƐX�ɂ̂ݕ��z����G�]�m�E���~�Y�U�N���i�� 10�j�́A�N���[���ɐB���s�����߁A�݂����̌̐����ߑ�]������Ă��邨���ꂪ�w�E����Ă���B���݁A��Ŋ뜜��ɂ̓��X�g����Ă��Ȃ����A����A�ڍׂȒ��������߂������̈�Ƃ�����B
(2) ��`�I�𗬂ƌ��S�Ȏ�q���Y�̓K���ێ�
�W�c��`�w�I�\���ɂ��A�ߐe��z�̈��e�����������`�I���l���̌������P���ȉ��ɗ}���邽�߂ɂ́A�܂�ׂ�Ȃ���z���N����Ɖ��肵�Ă��W�c�����薈����50�̈ȏ�̐����K�v�ł���A����ɁA�����ɂ킽���Ĉ�`�I���l�����ێ����邽�߂ɂ́A500�̈ȏオ�K�v�ł���Ƃ����Ă���B���ۂɂ́A��z�̕�A�J�ԁE�����̂�����l����ƁA����ɑ����̐��ؐ����K�v�ƂȂ�B
�������A����ł́A�W�c������̌̐����\���łȂ�����͂����݂���B���ۂɁA�̖��x�̒ቺ��W�c�̏��W�c���E���f���ɂ���đ��̂Ƃ̉ԕ��̌𗬋@����Ȃ��Ȃ�A���S�Ȏ�q���Y���s��ꂸ�A������X�V���j�Q����Ă��鎖��i�� 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13�j�͑����A���퐊�ނ̎�v�ȗv���ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȏꍇ�́A������W�c���m�ۂ��ďW�c���g�債�A��`�I�𗬂�������K�v������B
���}����ɂ���Ď��s�������ł́A�אڏW�c�Ƃ̋�����500m�ȏ㗣���ƈ�`�q�𗬂����҂ł��Ȃ��Ƃ���Ă���i�V�f�R�u�V�A�N���r�C�^���j�B�܂��A���}����ł������N�^�l�S���E�ł́A�̖��x���Ⴂ����n�ł�10m�ȓ��ɓ���̂��Ȃ��ƌ��S��q�͂T�����x���������Ȃ��B
![]()
(3) �X�V�T�C�g�̊m�ہE�n�o
�X�V�T�C�g�̊����������Ă���ꍇ�́A������W�c���m�ۂ��邽�߂ɁA�K�Ȋ��ɉ��P���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ꍇ�ɂ���ẮA�V���ɍX�V�T�C�g��n�o����K�v������B
���R�̊Ǘ������n����ӗѕ��̐����ɔ����ъ����ɂ���āA�X�V�T�C�g�̌������������A������X�V�Ɉ��e�����y��ł��錻�ۂ͂����Ύw�E�����B����܂ł̎��،�������A������̂ɂ���Č��������P�������ʁA�����̒蒅����Ȃǎ�����X�V�����i���ꂽ�Ⴊ�F�߂��Ă���i�� 3, 9, 12�j�B
�܂��A�_�n�]�p�Ȃǂ̓y�n�J���ɂ�銣�����Ő�������������鎖��́A���n������i�� 7, 10�j�Ŏw�E����Ă���A�Ë��Ȃǂ̐������ݔ��̔z�u�̌������ȂǁA��������h���K�v�Ƃ���Ă���B
����A�×������X�V�T�C�g�Ƃ���͔ȗэ\����i�� 4, 5, 13�j�ɂ��ẮA�×����̐�����W���Ȃ��͐�Ǘ����d�v�ȑ�ƂȂ�B
(4) ����s��
������̕ω���l�דI�����ɂ���āA����̑��݂������������킪�N�����鎖��������B�Ⴆ�A�P�V���E���i�M�i�� 4 �j�Z�A�J�V�A�F�l�דI�����Ƃ��̌�̒蒅�j�A���`�J���o�i�� 7 �I�I�C�^�h���F�������ɂ��N���j�A�G�]�m�E���~�Y�U�N���i�� 10 �T�T�ށA�I�I�n���S�E�\�E�E�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�ȂNJO���̍��s���{�F�������ɂ��N���j�Ȃǂł���B
�܂��A�̐��̌���ꂽ���킪����ɕa���Q��쐶�����ɂ��H�Q�ɂ���Ēv���I�ȑŌ�����ꍇ�������ď��Ȃ��Ȃ��B�����R�тɈ⑶�I�ɕ��z����g�E�q�ނ́A�V�J�̕��z�g��ɔ����Đ�������E�t�����H�Q���Ă���i�� 3�j�B�܂��A�}�c�ސ����ɂ���Q�i�� 1�j�A�ړ�����쐶���������M�ɂ��H�Q�i�� 8�j�ȂǁA��������A�n��̌̌Q�̑������������ꍇ�́A�K�Ȗh������s���K�v������B
![]()
(5) �W�c����A�E���n�O�ۑS
�̐����ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ�A����ł͏W�c�̊g��ɂ���`�q�𗬂̕������S�����҂ł��Ȃ��ꍇ�́A�W�c���ւ̕�A�i�� 3, 7�j����������K�v������B
�܂��A�ɂ߂Č��肳�ꂽ�n��W�c�̏ꍇ�́A��`�����ۑS���ނȂ����P�̍�Ƃ��Č��n�O�ۑS���K�v�ƂȂ�ꍇ������B���n�O�ۑS�ɂ́A�T�V�L��ڂ��ɂ���āA�����̂̃N���[�����m�ۂ���ꍇ�������B��q�R���̎�����ۑS����ꍇ�́A��q�̕������Ȃ��悤�ɍH�v���邱�Ƃ��]�܂����B
�����݁A�X�ъǗ��ǂ̕ی쎖�ƂȂǂɂ���āA���n�O�ۑS�̎��g�݂��s���Ă�����̂�����i�� 1, 2, 3, 8�j�B
(6) ��`�I�������̖h�~
��ї��ꂽ�n��ɕ��z�������́A�A���ꂼ��̒n��ň�`�I�ɕ������Ă��邱�Ƃ�����B��{�I�ɂ́A��`�q������h���A�n��ŗL�̈�`�I���l�����ێ����邽�߁A�قȂ�n��Ԃł̎�c�̈ړ��͍s��Ȃ����Ƃ��]�܂��i�� 4, 9, 13�j�B�܂��A�X�H���≀�|�p�Ƃ��Ď�c�����ʂ��Ă�����������i�� 9, 12�j�B����n�ɋ߂��n��ŐA�͂���ۂ́A�قȂ�n�悩��̎�c�͗��p���Ȃ��ȂǁA��c�̗R���ɗ��ӂ���K�v������B
�I�K�T�����O���i�� 8�j�ł́A�߉���ł���V�}�O�����������ꂽ���ʁA�߉���Ƃ̌��G���p�ɂɋN����A��`�I�ɏ����Ȍ̂̐����ɑ傫�ȏ�Q�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȏꍇ�́A�߉���̓O��I�ȏ����ƂƂ��ɁA�����̂̊m�ۂ��d�v�ȑ�Ƃ��ċ��߂���B
(7) �n��ɂ����闝���Ƌ���
�ȏ�̂悤�ȑ��L���Ɏ��{���邽�߂ɂ́A������̎���E��ɂ����Ă��A����n�̏��L�҂�n��Z���ȂǁA�n��ɂ����闝���Ƌ��͂͌������Ȃ��B
���n��ɂ��������̕ۑS�̂��߁A���j�^�����O�������n�̊Ď��Ȃǂ��A�n��Z���A�L�u�̉�ɂ���Đ��͓I�ɐi�߂��Ă��鎖��������i�� 1, 3, 5, 9, 12�j�B
�R�D������

����ۑS�̂��߂ɂ́A���ꂼ��̎�̎��Ԃ�m��A����ɉ����ēK�ȕۑS����I�A�����I���_�Ŏ��{����K�v������B
���݁A�ۊǑ��A���̂��悻�S��ɂP�킪��Ŋ뜜�Ƃ���Ă���A���b�h���X�g�ɐ�Ŋ뜜��Ƃ��Čf�ڂ���Ă���ؖ{�A����26�O����z���A���̂������悻�����͓쐼�����⏬�}�������ɌŗL�ɕ��z����B
�{���q�ł́A�k���n�⑶��𒆐S�Ƃ���14��̊���ɂ��Đ��ޗv���ƕۑS�ւ̑���q�ׂ��ɂ����Ȃ��B�������A�����ŏЉ���ȊO�̊���ɑ��Ă����ޗv����ۑS��͊�{�I�ɋ��ʂ���ƍl������B�n��ɂ��������ۑS�̎Q�l�ɂ��Ă���������K���ł���B
![]()
���킲�Ƃ̌���ƕۑS��

| ���j�t���� | |
| 1. ���v���^��q���ŗL | ���N�^�l�S���E�i�}�c�ȁj |
| 2. �ɏ��⑶�W�c | ���r��R�̃A�J�G�]�}�c�i�}�c�ȁj |
| 3. �{�B�����R�ш⑶ | ���c�K�^�P�g�E�q�A�q���o�����~�i�}�c�ȁj |
| ���L�t���� | |
| 4. �k�C���ƒ���Ɉ⑶ | �P�V���E���i�M �i���i�M�ȁj |
| 5. �R�n�͔Ȉ⑶ | ���r�\���i�M �i���i�M�ȁj |
| 6. �A�|�C�x�ŗL | �A�|�C�J���o�i�J�o�m�L�ȁj |
| 7. �ɏ��⑶�W�c | ���`�J���o �i�J�o�m�L�ȁj |
| 8. ���}���ŗL | �I�K�T�����O�� �i�N���ȁj |
| 9. ���C�u�˗v�f | �V�f�R�u�V�i���N�����ȁj |
| 10. �k�C���ƐX�Ɉ⑶ | �G�]�m�E���~�Y�U�N�� �i�o���ȁj |
| 11. �k�C���ƒ���Ɉ⑶ | �N���~�T���U�V �i�o���ȁj |
| 12. ���C�u�˗v�f | �n�i�m�L�i�J�G�f�ȁj |
| 13. �k�C���Ɠ��k�E�����Ɉ⑶ | �N���r�C�^���i�J�G�f�ȁj |
�@

![�G�]�m�E���~�Y�U�N��](Photo/PracemoG/PR73.png)




![�A�J�G�]�}�c](Photo/PglehniiG/PG73.png)







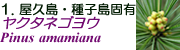
![�A�J�G�]�}�c](image/P_glehniiM.png)







![�G�]�m�E���~�Y�U�N��](image/P_racemosaM.png)


