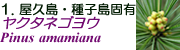種の特徴

ヤチカンバは、1958年に北海道の更別村で発見され、新種B. tatewakiana M. Ohki et S. Watanabeとして報告された。さらに、1974年に別海町でも本種が見つかった。その後、分類の見直しにより、サハリン・朝鮮・中国東北・ウスリーに分布するヒメオノオレB. ovalifolia Rupr.に本種は含められた。B. tatewakianaは二倍体とされ、四倍体のコウアンヒメオノオレB. fruticosaの祖先種とする見解もある。ただし、核DNAを調べるとヤチカンバはB. ovalifoliaと同じく四倍体のようだ。
カンバ類(カバノキ属)の多くは高木だが、ヤチカンバは、成熟しても樹高1.5mほどの低木にしかならない。このような矮性のヒメカンバ類は北極周辺のツンドラ地帯に分布している。このヒメカンバ類は氷河期に日本列島にも分布していたと考えられており、本種とアポイカンバの2種が北海道に生き残っている。ヤチカンバは、生育地が限られており、環境の変化を受けやすい湿原に生育する。更別の生育地は北海道の、別海町の生育地は別海町の天然記念物に指定されている。それらの指定区域の面積は、更別で3 ha、別海で4.6haである。また、ヘクタールあたり株の密度は、更別で1,700、別海で6,500である。これらの生育地は直線距離で約170km離れており、種子や花粉の移動は考えにくく、互いに隔離されていると言える。
ヤチカンバは、湿原の塚状の高まり(ヤチボウズ)の上に株立ちし、5-15本の幹を持つ株が多い。本種は、根元に萌芽器官が分化していて、旺盛な萌芽再生によって株を維持していると考えられる。別海では、24年未満ですべてのシュートが枯死し、若いシュートに置き換わると考えられている。このようにシュートを置き換えながら、株自体はきわめて長い期間生き延びているようだ。
ヒメカンバ類は、地面を這う枝から萌芽して株分かれし、遺伝的に同じ株(クローン)を離れた場所に作ることができる(無性繁殖)。更別と別海で、異なるヤチボウズに生育する50株ずつを調べたところ、遺伝的に異なる個体数は更別で49、別海で45となった。よって、ヤチカンバの無性繁殖の頻度は低く、遺伝的に異なる個体数は株数とあまり変わらないと言える。
開花結実している株は更別で特に多く見られるが、更別でも別海でも実生はほとんど見つからない。カンバ類の実生は、撹乱によって生じた明るい裸地に定着することから、現状の生育地では実生更新がほとんどできないと思われる。
衰退要因

生育面積の減少と湿原の乾燥化により、特に更別でヤチカンバ群落が衰退している。
更別の生育地は、1958年には600 haの更別湿原(泥炭地)の周辺に、幅20-100 m、長さ1,500 m(3-15 ha)の範囲にあったとされているが、1995年には2.14 haになっていた。1963年の天然記念物指定以前には、馬の放牧や野火の影響を受けていたと言われる。生育地の周囲は、畑作農地になっている。1980年代に深さ1m、幅1.5mの排水溝が指定区域の周囲に掘られたため乾燥し、湿原植物のミズゴケ類やスゲ類が消失し、湿原外植物のミヤコザサやワラビ,オオイタドリが侵入している。また、山菜採りなどにより人の踏みつけ跡が随所に見られる。
別海の生育地がある西別湿原は、1965年には68 haの面積があった。1970年代後半から急速に牧草地に転換されて湿原中心部が消失し、元の湿原が3つに分断された。1995年には、これらを合わせた面積が16 haに減少した。これら3つ湿原のすべてにヤチカンバが分布している。天然記念物の指定区域は、東側の最も大きい湿原にあり、1979年に0.5 haが指定され、2003年に4.6haに拡大された。指定区域の西部には明渠が掘られており、湿原外植物の侵入や乾燥化が懸念される。更別の生育地と比べて、チャミズゴケやハナゴケ、ヌマガヤ、ワタスゲなどが生育する湿原の環境が維持されている。クロバナハンショウヅル、ヒメツルコケモモ、カンチスゲ、イトナルコスゲ、ホロムイクグなどの希少な湿原植物も生育している。湿原の周囲からのハンノキやミヤコザサの侵入やミズゴケ採取、踏みつけによる影響が一部で認められる。
このように、環境条件は別海より更別で悪く、個体数も別海より更別で少ない。しかし、核DNAの遺伝的変異を調べたところ、遺伝的多様性は別海と更別でほぼ同じで、遺伝的組成も更別と別海との間でほとんど共通していた。葉の形態を調べたところ、更別の葉は細長く、別海の葉は短く幅広い傾向があったが、それらの変異は大きく重なっていた。よって、更別と別海との間で隔離されているにもかかわらず、遺伝的分化や葉形態の違いは小さく、更別でも遺伝的・形態的変異が維持されていると言える。この理由として、株の寿命が長く世代交代があまり進まなかったことなどが考えられる。
一方、葉の左右対称性の歪みは、別海より更別で大きかった。カバノキ属の葉の左右対称性は、環境汚染や低温などのストレスによって歪むので、湿原外植物の侵入や乾燥化によって、別海より更別でヤチカンバがストレスを受けていると考えられる。

写真2.天然記念物指定地(更別村)
保全のための課題と対策

まず、現存する個体を生かすことが最も重要である。なぜなら、現存個体は過去の遺伝的変異を受け継いでおり、長生きすることができるからである。特に、生育地の劣化が進んでいる更別で、積極的な対策が望まれる。具体的には、次のとおりである。
①生育地内への立ち入り規制と競合種の排除
ヤチカンバの生存率を上げるには、山菜採りなどによる立ち入りを禁止し、湿原外植物を取り除くことが考えられる。特に、植物高が高くなるオオイタドリは、ヤチカンバを被圧して枯死させるので、その除去が必要である。
②湿原環境の復元
抜本的な対策として、地下水位を上げて湿原環境を復元することが重要である。生育地内や周囲に掘られた明渠を埋め戻したり、近くの水路からその明渠まで連絡して水を引くことも考えられる。ただし、ヤチカンバは、湿原内ではやや乾燥したヤチボウズ上に生育することから、過度の湿地化に注意すべきだろう。
③移植による生育地の復元
不幸にも、更別か別海のどちらかの生育地が失われたら、残ったもう一方の生育地からの移植によって失われた生育地を復元することは妥当だろう。更別と別海の遺伝的・形態的変異は大きく重なっているので、人為的移植によってほとんどの遺伝的変異は回復できると考えられる。